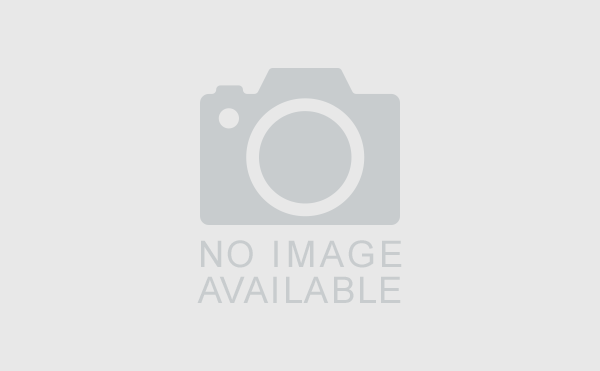【超かんたん!】「ドレミの歌」ウクレレ弾き語りに挑戦!
ウクレレで、超かんたんにいろいろな曲に挑戦!
歌うこと、演奏することを、とにかく、楽しみましょう!
そして、楽しくがんばって、今日1日をステキに過ごすことのお手伝いが、ウクレレでできればうれしいです!
ということで、今回の曲は、「ドレミの歌」です。
この曲は、ミュージカル、サウンド・オブ・ミュージックの中の曲で、
作詞;オスカー・ハマースタイン2世
作曲;リチャード・ロジャース
です。
歌はジュリー・アンドリュース、日本ではペギー葉山のものが有名ですね。
また、僕たちが、一般的に歌っている日本語の訳詞もペギー葉山によるものです。
6つのコードですが、実質5コードで演奏できます
使うコードは
C G7 F C7 D7 E7
です。

C7はCの兄弟みたいなもので、Fのコードの前に鳴らすと、効果的です。
また、押さえ方も簡単なので、今回の曲は実質5コードで、できます!

ウクレレで歌の音程を安定させよう!
音楽の要素はリズム メロディ ハーモニーと言われていますが、演奏にも要素があります。
人によって、重要視する要素は違ってくると思いますが、ボク個人としては音程、リズムキープ、そしてノリが重要と思います。
そして、こららの要素によって、「上手い」とか、「味がある」とか、「スゴイ!」とか、「感動した!」とか、評価されるわけです。
この中で、まず、音程というのが、わかりやすいというか、目立つ要素です。
音を外してしまうと、いわゆる、音痴とか言われて、ヘタクソと思われちゃいます。
ちょっと、余談になりますが、この音痴という言葉も、差別的なニュアンスがあるとのことで近々、呼称の言い換えが検討されているみたいで「歌の不自由な人」が有力とのことです。
「歌の不自由な人」なんて、余計に変な感じがするのですが、ここでの言及はこれくらいにします。
話を元に戻します。
音を外すと、ヘタクソと言いましたが、実は、必ずしも、音を外している人がみんなヘタクソではありません。
多少、音が外れていても、カッコよく歌っているアーティストはかなり多くいます。
彼らは、リズムのノリとか、歌い回しで、ちょっと外れた音程も含めて、燦然(さんぜん)たる個性として表現できているからです。
なので、音は少々外しても大丈夫ですが、やはり、ある程度、自分がどんな音を出しているのかわかっていることに越したことはない。
というわけで、もし、今あなたが、音程の取り方に不安を感じているのなら、この方法は試す価値、大いにアリです。
まず、最初にウクレレなし、なにもなしで、で歌ってみます。
ゆっくりと。
そうすると、曲の中の、自分がとりにくい音(音程が不安な音)がわかります。
次に、ウクレレの単音でメロディをなぞる。
ウクレレの単音弾きですね。つまり、ウクレレでメロディを弾きます。
この作業は音程の練習にもなるし、ウクレレを歌わせる練習にもなって、一挙両得です。
また、このようなデュアルタスクは脳や認知力アップにも効果的です。
そして、最後に、ウクレレの単音弾きと合わせて、歌います。
これも、ゆっくりと行うことが、超大事です。
このようにして歌うと、メロディの輪郭がすごくはっきりして、歌っていても、音程がたしかに安定してくるのがわかります。
歌っていても安心感、安定感を感じることができると思います。
この方法で、音程のよりどころとなる、メロディのガイドがつくことになります。
かなりの確率で、音程の安定感が格段に良くなりますね。
また、この方法は、ウクレレがあれば、手軽に実践できます。
極端な話、慣れてくれば、寝転がってもできます。
もうひとつのポイントは、この作業を「遊び感覚」「ゲーム感覚」でやることが大切。
遊び感覚で行うと、作業の定着率が、義務感覚で行なった場合よりも、高い率で定着します。
このことは、いろいろな実験や調査で証明されていますね。
まあ、楽しければ、その作業は何度でも繰り返しできます。
そうなれば、当然、定着率が高くなること、イメージ的にもわかりますね。
そして、定着すれば、習慣になります。
習慣形成こそ、上達のいちばん大事な要素です。
まずは、主体的な学びの習慣形成です。
なので、5分でも3分でも良いので、ウクレレを触る楽しみタイムを作りましょう!
主体的な学びの習慣ができれば、深い学びへの挑戦も楽しくなります。
良い習慣のサイクルを、このように、少しの工夫で作っていきましょう。
それをウクレレで作っていきましょう!
ということで、今回もここまでのお付き合い、ありがとうございます!
では、次回のウクレレタイムでお会いしましょう!