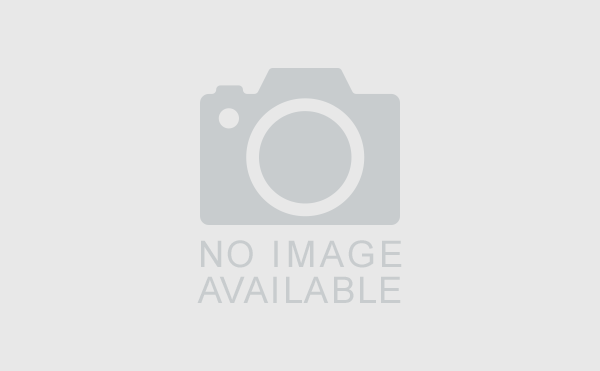6月の養生
食養生
東洋医学では6月から8月を夏の季節としてくくります。
6月はその最初の月で、本来、暑さも序の口のはずなのですが今年は様子が違います。
5月ですでに真夏のような気温になり、そのため熱中症になる人も少なくありません。
この急激な温度の上昇に身体がついて行かずに体調を崩したり、熱中症以外でも風邪をひいたり胃腸障害を起こしている方も多いです。
陽気は活動するために大切なものですが、余分な陽気は発散させないといけません。
とくに今年のような気候の時は、この陽気の発散がより大切になってきますね。
また6月には梅雨があります。この時期には余分な湿への対処も重要。
水分の代謝を促し、熱を逃がす食材を摂ることがポイントになります。
さて、生活のリズムですが、朝は早く起きるを基本に考えましょう。夜が遅くなった時には昼間に短時間の昼寝の時間をとることができればいいですね。
お仕事等の理由で早朝に起床が難しい場合は冬の時期より30分早い起床にトライしてみてください。
そして炎天下、気温の高い室内での作業には必ず休憩を入れましょう。また、適度な運動で汗を出すことと、エヤコンや冷たいもので身体を冷やし過ぎないことも肝心です。
基本の食材
アスパラガス キュウリ 冬瓜 トマト ピーマン オクラぶどう さくらんぼ ブルーベリー ラズベリー スイカ 鮎 カツオ はも うなぎ
梅雨の時期の「湿」と「熱」対策の食材
かぼちゃ キュウリ さやいんげん さつまいも いちじく ぶどう マンゴー スイカ とうもろこしのヒゲ 鮎 イワシ 穴子
健康ツボ療法
内関(ないかん)→体温調節
気温が上がっているのにあまり汗が出なくて体の中に熱がこもっている感じがしたらこの内関穴を押してください。
自律神経の乱れを正してくれる効果があります。
場所は手首のシワの中央から指3本分くらいのところ。少し痛みを感じるくらいの強さでじわーっと5回ほど押します。
このツボは乗り物酔いにも効果的です。

今!やるべき熱中症対策!
熱中症は、気温の高い環境で生じる健康障害 (めまい・シビれ・頭痛など) の総称です。
また「かくれ脱水」という状態があり脱水症になっているにも関わらず自覚症状のない状態です。深刻な状態になるまで明確な症状が出にくく、早い段階で有効な対策がとれないやっかいな状態です。
体内の水分が2%失われるとのどの渇きを感じ、運動能力が低下しはじめます。3%失われると、強いのどの渇き、ぼんやり、食欲不振などの症状がおこり、4~5%になると、疲労感や頭痛、体温上昇、めまいなどの脱水症状があらわれます。
そして10%以上になると、死に至ることもあります。
体から出ていく水分量は、もちろん個人差はありますが、おとなで1日2リットル以上です。これは排泄や発汗、そして呼気から排出される総量です。
そして出て行った水分は当然補給しなければいけません。ところがこの補給が足らなくなることが往々にして起こります。
そのケースとしては
筋肉量が少ない場合です。以前もお伝えしましたが水分を保持できるのは筋肉です。筋肉量が低下している高齢者、若い方でも運動不足などで筋肉量が低下している方は注意が必要です。
また内臓の働き、とりわけ体内の水分量をコントロールする腎臓の働きの低下も脱水につながります。加齢による機能低下だけでなく、エアコンなどで体を冷やすと内臓の働きが悪くなるので注意しましょう。
そして加齢によるもの、または仕事などへの意識の集中、もしくは飲酒での酩酊状態による感覚機能の低下で喉の渇きに気付きにくくなる場合があり、熱中症のリスクが高まります。
飲酒はアルコールの分解時に水分を消費し、尿量を増やすのでよけいに体の水分を奪ってしまいます。また血圧を下げる薬の中にも利尿作用を含んでいるものがあり気をつけないといけませんね。
対策については、こまめな水分補給です。とくに、起床時・入浴後・運動後・外出後・飲酒後は必ず行いましょう。水分だけでなく、塩分等のミネラルの補給も行なってください。
時にはスポーツドリンク、経口補給水、またはフルーツなどを取り混ぜて、本人の好みや体調に合わせて変化をつけて、楽しく水分補給出しながら手強い夏を乗り切りましょう!